所得税とは?仕組みから計算方法までわかりやすく解説
毎年の確定申告や年末調整で必ず関わる「所得税」。給料から天引きされているものの、仕組みや計算方法を詳しく理解している人は少ないかもしれません。所得税は国の税収の中でも大きな割合を占める税金であり、私たちの生活と密接に関わっています。この記事では、所得税の基本から計算の流れ、控除や注意点まで、できるだけわかりやすく解説していきます。
所得税とは?
所得税は、個人の1年間の所得に対して課される税金です。所得とは「収入から必要経費や控除を差し引いた金額」のことを指します。
- サラリーマンの場合:給与収入から給与所得控除を差し引いた金額
- 自営業やフリーランスの場合:売上から経費を差し引いた事業所得
つまり、単純に「収入額=課税対象」ではなく、必要な経費や一定の控除を差し引いた後の金額に対して税金がかかります。
所得税の大きな特徴「累進課税」
所得税の大きな特徴は「累進課税」です。これは、所得が多いほど高い税率が適用される仕組みです。日本の所得税率は段階的に設定されており、2025年現在は以下のようになっています。
- 195万円以下:5%
- 195万円超〜330万円以下:10%
- 330万円超〜695万円以下:20%
- 695万円超〜900万円以下:23%
- 900万円超〜1,800万円以下:33%
- 1,800万円超〜4,000万円以下:40%
- 4,000万円超:45%
この仕組みにより、高所得者ほど多くの税金を負担する一方、低所得者の負担は比較的軽くなっています。
所得税の計算の流れ
所得税は大きく次の手順で計算されます。
- 収入を合計する
給与、事業、年金、利子、配当など、すべての収入を集計します。 - 所得を計算する
収入から必要経費や給与所得控除などを差し引いて「所得」を出します。 - 所得控除を差し引く
所得から「基礎控除」「扶養控除」「医療費控除」「社会保険料控除」などを引きます。これにより課税対象となる「課税所得金額」が決まります。 - 税率をかけて税額を求める
課税所得金額に応じて上記の累進税率をかけます。 - 税額控除を差し引く
配当控除、住宅ローン控除などを差し引き、最終的な所得税額が確定します。
サラリーマンと自営業の違い
サラリーマンの場合は会社が「年末調整」を行ってくれるため、自分で確定申告をする必要がない場合が多いです。ただし、副業収入がある場合や医療費控除を受けたい場合は、確定申告が必要になります。
一方、自営業やフリーランスは、毎年必ず確定申告を行い、収入と経費を自分で計算して所得を申告します。その分、経費として認められる範囲が広く、節税の余地もあります。
所得控除の代表例
所得税を計算する上で重要なのが「控除」です。代表的なものをいくつか紹介します。
- 基礎控除:すべての人に適用される控除(48万円)
- 扶養控除:扶養している家族がいる場合に適用
- 医療費控除:年間の医療費が一定額を超えた場合に適用
- 社会保険料控除:健康保険や年金保険料を支払った場合に適用
- 生命保険料控除:生命保険や個人年金保険の支払いによる控除
これらの控除を上手に活用することで、課税所得を減らし、結果的に支払う税額を抑えることができます。
確定申告と年末調整
- 年末調整:サラリーマンが毎月の給与から天引きされた税額を年末に精算する仕組み。通常は会社が手続きを行います。
- 確定申告:1年間の所得と控除を自分で計算し、税務署に申告する手続き。自営業者は必須、給与所得者でも副業や控除の申請がある場合に必要です。
所得税を理解するメリット
所得税は単に「取られるもの」ではなく、制度を理解することで次のようなメリットがあります。
- 節税のポイントが見える
- 家計の見直しにつながる
- 将来のライフプランを立てやすくなる
特に控除制度や確定申告を正しく活用すれば、税負担を軽減できる可能性があります。
まとめ
所得税は、私たちの収入に応じて負担する国の税金であり、累進課税制度を通じて公平性を保っています。収入から経費や控除を差し引き、課税所得に税率をかけて計算されるという仕組みを理解しておけば、年末調整や確定申告もスムーズに行えます。
普段はあまり意識しないかもしれませんが、所得税の知識を持つことで生活に直結するお金の仕組みを理解でき、将来に備えることにもつながります。
参考リンク
- 国税庁「所得税の仕組み」
- 国税庁「確定申告書等作成コーナー」

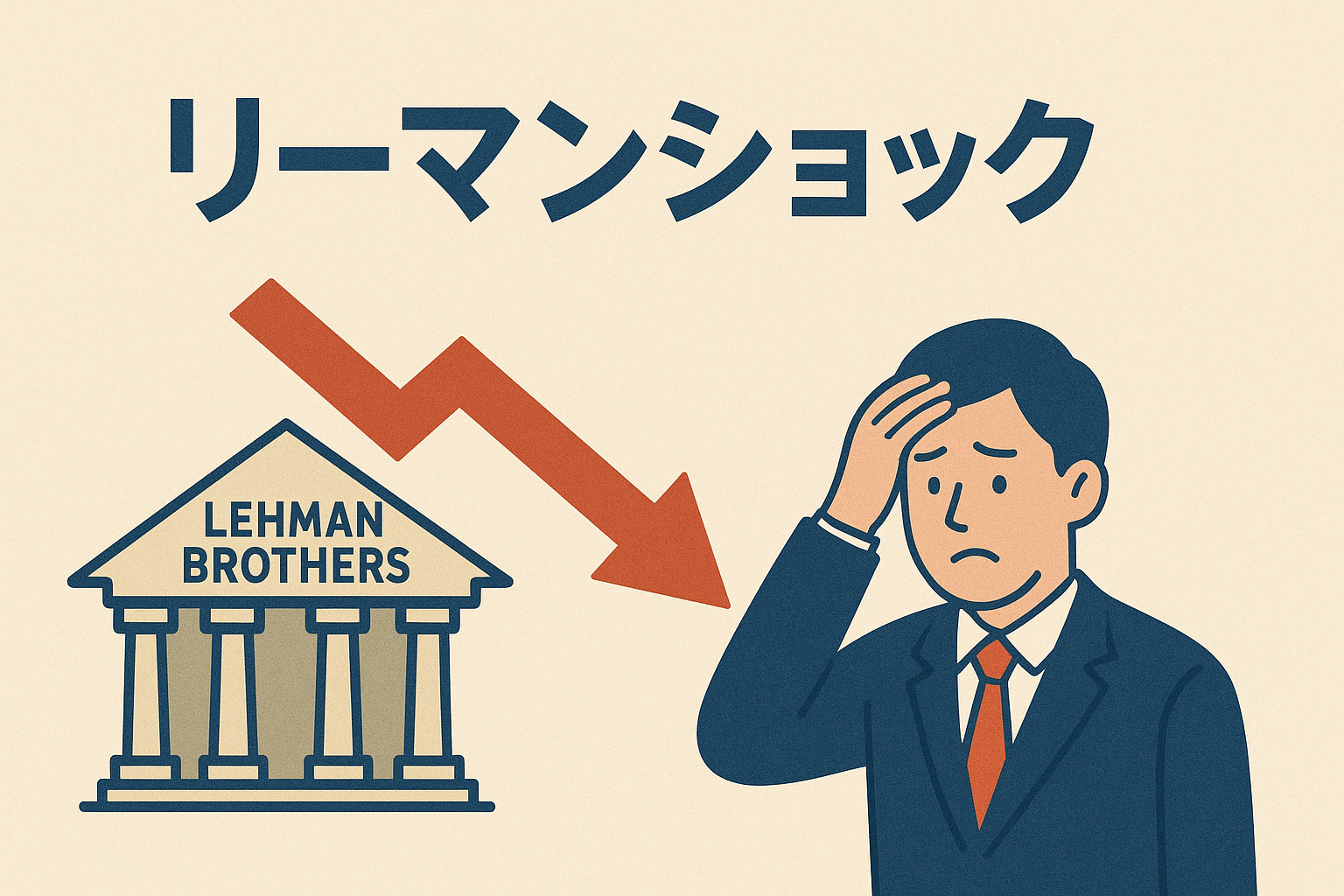

コメント