ステーブルコインとは?仕組みと特徴をわかりやすく解説
暗号資産(仮想通貨)の分野は成長を続け、日々さまざまな新しいサービスや仕組みが登場しています。その中でも「ステーブルコイン」という言葉を耳にする機会が増えてきました。
ステーブルコインは名前の通り「安定したコイン」という意味を持ち、価格の変動が少ないことを目的として作られています。この記事では、ステーブルコインの基本的な仕組みや種類、メリットとリスクをわかりやすく解説します。
ステーブルコインとは?
ビットコインやイーサリアムといった暗号資産は、投資対象として人気を集めていますが、価格の変動が大きいのが特徴です。ときには1日で数%から数十%も上下することがあり、日常的な決済や送金に使うには安定性に欠けると指摘されてきました。
そこで考えられたのが「ステーブルコイン」です。これは法定通貨や資産と価値を連動させ、価格を安定させる仕組みを持つ暗号資産のことです。
ステーブルコインの種類
ステーブルコインは仕組みによって大きく3つに分けられます。
法定通貨担保型
米ドルやユーロ、日本円などの法定通貨を裏付けとして発行されるタイプです。
代表例は「USDT(テザー)」や「USDC」です。1コイン=1ドルを目標に設計されており、発行体が保有する資産によって信頼性が担保されています。
暗号資産担保型
ビットコインやイーサリアムなど、他の暗号資産を担保に発行されるタイプです。
価格変動の影響を考慮し、担保を多めに預ける仕組みが採用されます。代表例は「DAI」で、スマートコントラクト(自動契約プログラム)によって運営されています。
アルゴリズム型
特定の資産を担保にせず、需給に応じてコインの供給量を調整し、価格を安定させる仕組みです。
理論的には魅力的ですが、過去に大規模な価格崩壊を経験した事例もあり、信頼性には課題があります。
ステーブルコインのメリット
- 価格の安定性
値動きが大きいビットコインなどに比べて安定しているため、決済や送金に利用しやすい。 - 国際送金の効率化
従来の銀行送金に比べて、手数料や時間を大幅に抑えられる可能性がある。 - 資産の避難先として活用できる
投資家が値動きの大きい暗号資産から一時的に資金を移す「安全な中継地点」としての役割を果たす。
ステーブルコインのリスク
- 発行体の信用リスク
裏付けとなる資産が本当に保有されているか不透明な場合、1コイン=1ドルを保証できない恐れがある。 - 規制の影響
各国の金融当局がステーブルコインをどのように規制するかによって、利用環境が大きく変わる可能性がある。 - システム上のリスク
暗号資産担保型やアルゴリズム型は、市場の混乱や技術的な脆弱性によって価格維持が難しくなることがある。
まとめ
ステーブルコインは、暗号資産の世界に安定性をもたらす重要な仕組みです。国際送金やデジタル決済の利便性を高める一方で、発行体の信頼性や規制環境によるリスクも無視できません。
今後、金融機関や企業がどのように活用していくかによって、ステーブルコインの役割はさらに広がっていく可能性があります。暗号資産に関心のある方は、投資対象としてだけでなく、日常生活における活用や社会的な影響についても注目していくとよいでしょう。
利用を検討する際には、必ず公式情報を確認し、仕組みとリスクを理解したうえで判断することが大切です。
参考リンク
- 金融庁 暗号資産に関する情報
https://www.fsa.go.jp/policy/virtual_currency/index.html - 日本銀行 デジタル通貨に関する取り組み
https://www.boj.or.jp/announcements/release_2021/rel210409a.htm

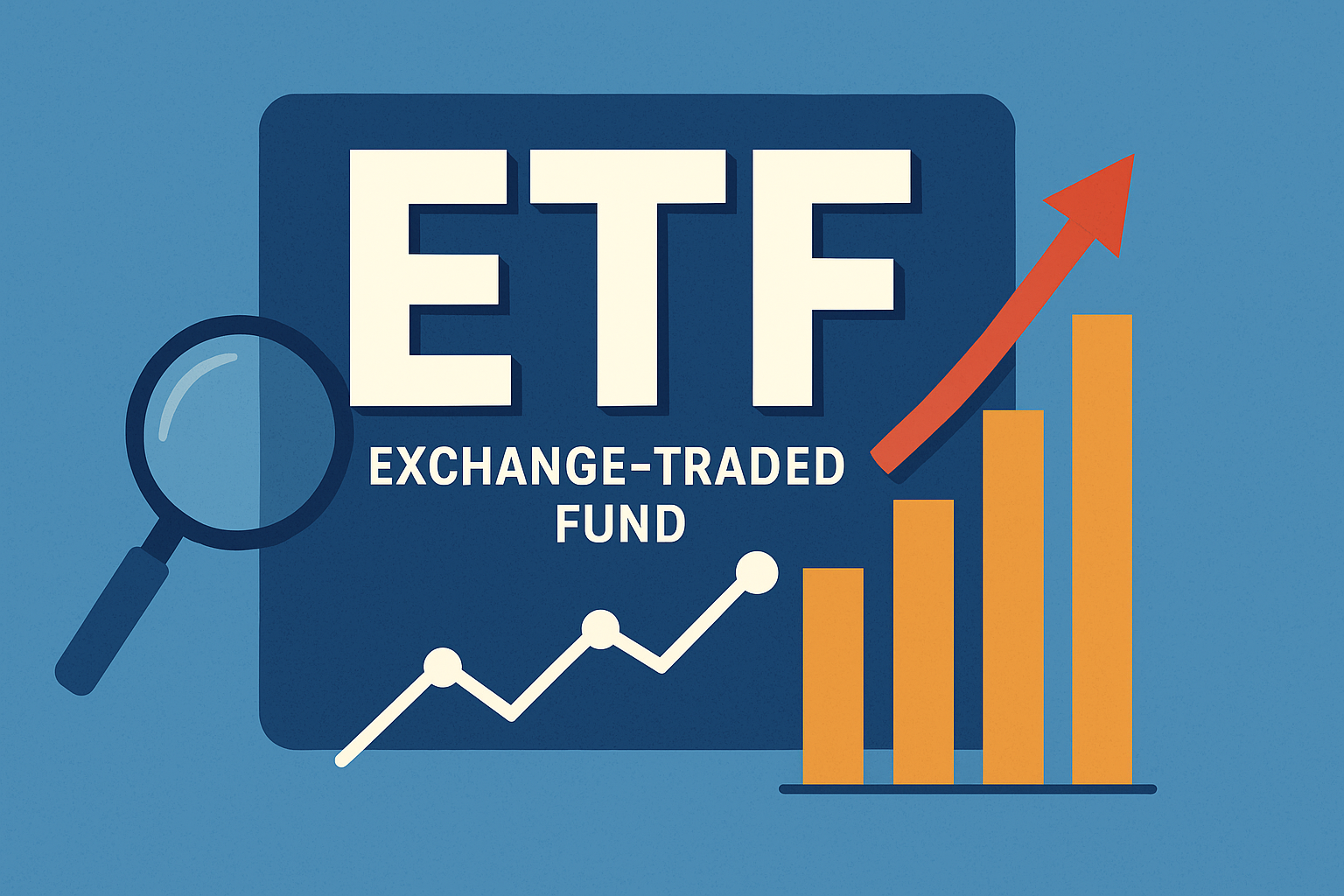
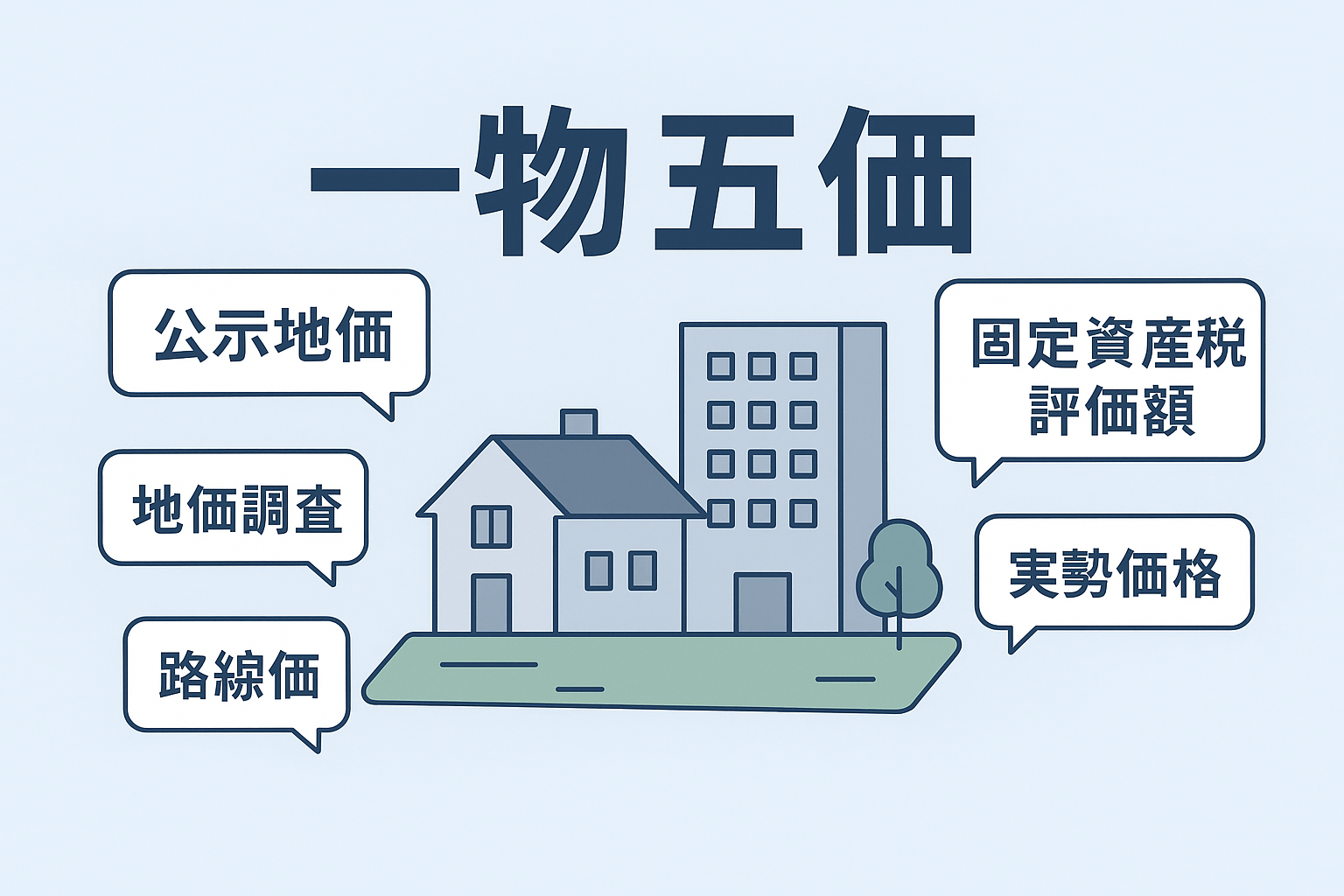
コメント